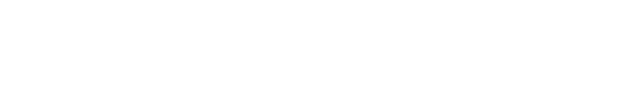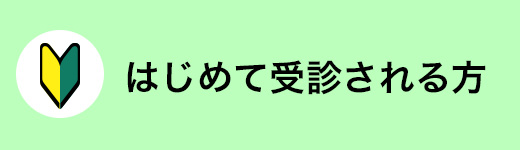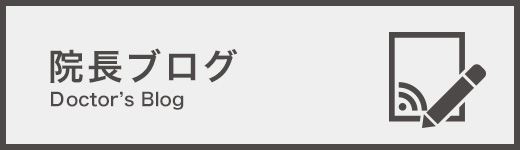ポリヴェーガル理論とは(Ver1.0)
摂食障害の診療をしていると、トラウマ・PTSDで苦しんでいる患者さんと出会うことが多いです。
しかし、その前にも、私が脳神経内科で働いているときにも実は出会っていたと思うのです。
急激に手足が脱力して歩けなくなってしまったり、気が遠くなってしまい、ひどいときは失神してしまう患者さんを数人担当したことがありました。
脳MRI、脳波、24時間心電図、採血検査などいくつかの検査を行い、「神経調節性失神」「体位性頻脈症候群」「転換性障害」「(脳波では異常がないが)てんかん疑い」など、その場その場で診断してきたと思います。
病歴にはかなり精神的に強いショック、もしくは長期間の苦しみが示唆された患者さんがほとんどでした。そのため、精神科の先生にお願いすることも多かったですが、その方々が今どうされているのか。適切な診療が受けれられたのか、申し訳ないことですが、わかりません。
適切に話を聞く能力、それを受け止める臨床力がなかったと反省しています。
その後、脳神経内科、急性期の医療現場から一歩引かざるをえない時期がありましたが、そんな中で出会ったのが「複雑性PTSD」と「ポリヴェーガル理論」でした。特に、今回のタイトルにある「ポリヴェーガル理論」は自分にとって内科・心療内科・精神科をつないでくれる理論で、衝撃を受けました。
トラウマ・PTSDで困っている患者さんからは、過眠・不眠や、緊張・脱力症状について相談を受けることがとても多いのですが、これらはトラウマ、つまり危険に対する自律神経系の反応であると考えられます(他の原因が除外できれば、ですが)。
特に、幼少期から長期間、不安な環境で育ってきた方に多い激しい自律神経失調症状が、ポリヴェーガル理論を通して見るとよく説明できるのです。
「ポリヴェーガル理論」は、ステファン・ポージェス博士が提唱した「自律神経系の機能に関する見方」についての「仮説」です。まだ医学的に正しさが証明されているものではありません。
ポージェス博士は、赤ちゃんの心臓の拍動が変化することについて研究をしている中で、迷走神経の活動に着目しました。迷走神経は、全身に広がる神経の束。運動神経・感覚神経も含まれますが、その多くが副交感神経です。副交感神経は端的に言えばリラックスする方向に身体を調節します。
しかし、迷走神経の活動が、心臓の速さや強さを、ゆっくりちょうど良く調節する健康的な働きもあるのに、急激で致命的な徐脈も引き起こすこともある。という矛盾した方向性になってしまうのはなぜなのか。
その現象を説明するために、ポージェス博士は解剖学を勉強した結果、自律神経系を「交感神経と副交感神経の2つ」ではなく、「古い副交感神経、交感神経、新しい副交感神経の3層」に分けて考えるという理論にたどり着いたのです。これがポリヴェーガル理論の核です。
交感神経系は恐怖・脅威に対して「闘う、または逃げる(fight or flight)」のための神経です。動くことによって身体を守ります。
交感神経が優位に働くと心臓が速く強く動き、血圧が上がり、呼吸は荒く大きくなり、筋肉は緊張します。これはイメージ通りです。
対して、「進化的に古い副交感神経」=背側迷走神経系 は両生類・爬虫類の時代からの脊椎動物全般に存在しており、「体をシャットダウン」
してエネルギー消費量を抑え、外敵に対して「死んだふり」をします。過剰なリラックス状態を導く副交感神経です。この神経系は、体を完全に休息させて、身体を修復させるのに非常に重要な働きをしています。血圧を下げ、筋肉に力が入りにくくなります。
そして「進化的に新しい副交感神経」=腹側迷走神経系は、哺乳類に特有と考えられています。仲間とリラックスしながら安心感のあるコミュニケーションをしているときに働く、「社会的関与システム」としての役割です。あくまで安全な状態において、上の2つの交感神経系、背側迷走神経系をうまく抑えています。
顔まわりの運動神経はこの腹側迷走神経系グループに属しているため、リラックスした表情、声のトーン、食べ物を飲み込む、などにも関係していると考えられます。精神的な緊張がこのあたりに出やすいですよね。腹側迷走神経系がうまくはたらいていると、これらの動作や運動が緊張、こわばらずにでき、バランスが保たれやすいと考えられています。
基本的にヒトとしては、新しい腹側迷走神経系で、仲間と「群れ」で問題や脅威を解決したいですし、時には交感神経系が前にでて、戦闘モードになることもあります。
しかしとてつもなく大きな恐怖・脅威にさらされると古い背側迷走神経系が働き、急にシャットダウンしてしまう状態になってしまいます。急に「凍りつく(freeze)」ように動けなくなったり、体が重くなったり、ぼーっとしたり、諦めたりしてしまうということです。
問題は、慢性的に恐怖・恐怖にさらされているヒトの場合、この背側迷走神経系によるシャットダウンが起こりやすくなっていると考えられる点です。それを証明するデータは特にありませんが、臨床的には本当にそう感じます。
上記がポリヴェーガル理論が、トラウマ・PTSD患者さんの自律神経症状をどう説明できるのか、という考え方のごくごく簡単にまとめた基本となります。
ポリヴェーガル理論については重要だと思っているため、いくつかの記事に分けながら、今後もブログでご紹介していきたいと思っています。
参考文献)
ステファン・W・ポージェス著、花丘ちぐさ訳、『ポリヴェーガル理論入門 心身に変革を起こす「安全」と「絆」』春秋社、2018
津田真人著 『「ポリヴェーガル理論」を読む』星和書店、2019
(今はもっとわかりやすい本がたくさん出版されていますが、この2冊が日本では元祖なのではないかと思います。)