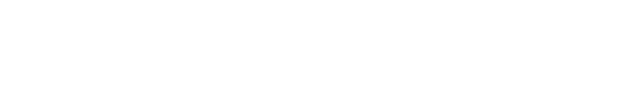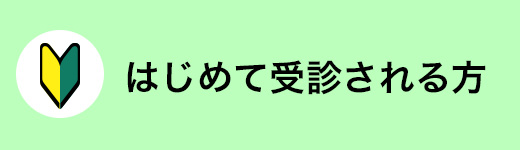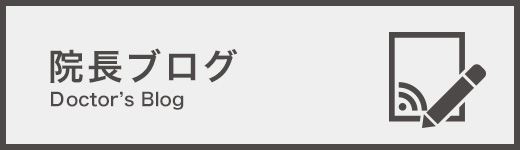「過食は症状である」という原則について(Ver.1.1)
「過食」、「むちゃ食い」については、当院の治療の重要なテーマでありすぎることもあり、
公表して皆さんに読んでもらう文章にまとめるのが難しく、後回しになっていました。
クリニックにおいて摂食症を診療することにより、「過食」についての治療の比重が高いため、
新しい発見もあったり、患者さんごとに合うアプローチを探してアレンジしたり、少しずつアップデートしているつもりですが
その上で、まずは一貫して変わることのない「過食」「むちゃ食い」の考え方の原則を紹介します。
それはタイトルの通り、「過食は症状である」ということです。
水島広子先生の著書から引用させていただきます。
『 過食の場合、最も意味のある心理教育は「過食は症状であり、本人のコントロールの及ばないものである」という点を明らかにすることである 』
(水島広子著 「摂食障害の不安に向き合うー対人関係療法によるアプローチ」創元社こころ文庫)
「食べる」という動作がどうしても日常的なものであり、
「食べたいから食べる」、と多くの人が思っていることであるため、
どうしても「過食」は食べたいだけでしょ、と考えてしまいがちです。
そうなると、「過食」は、「意思の強さ」でコントロールできるという誤解が生まれてしまいます。
過食は症状ですので、例えばインフルエンザウイルス感染症で発熱が出るのと同じです。
ということは、「過食を(根性で)やめなさい」と言うことは「39℃の熱を(根性で)下げなさい」と
言っていることになります。
私は以下の場合を除き、「過食をしないように」と言うことはありません。それもお願いベースです。
唯一、重症の低体重からのリフィーディング症候群で、リンやカリウムが下がると致命的になるような状態で、かつどうしても外来で診察しなければならない状況のときだけです(基本的には入院適応です)。
さて、「過食が症状である」、ということは、周囲の人にわかっていただきたい摂食症の基本原則なのですが、それを理解・そして実感することは、過食、むちゃ食いで苦しんでいる患者さんにも大きな意味があります。
それは、「過食してしまった」というストレスをかき消すために過食をしてしまいがちだからです。
「過食をしてしまった、なんて意思が弱い人間なんだ、もう二度としない」などの不快で受け入れられない感情が、そのまま過食のエネルギーになってしまうことがあるのです。
「過食は症状といわれても、自分が弱い、意思が弱いことの言い訳にしているだけだからそう考えたくない」と考える患者さんは非常に多いです。
たしかに過食の治療プロセスにおいて、ある一定の意思の力、決意は必要になりますが、それ以上に、「治療のための準備と工夫」が超重要です。
ここで、過食したストレスによる過食を勝手に「過食ストレス過食」と名付けますが、このパターンの過食を減らすには、
「過食」をしてしまったことは摂食症の症状であることを受け入れ、どこを工夫すれば違う行動になれるかを考える必要があります。
その人によって、できている準備、できていない準備があり、どこから工夫できるのかが違っています。
それを一緒に考える場として、ぜひ当院にご相談いただければと思います。