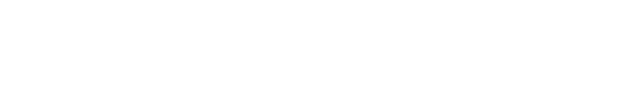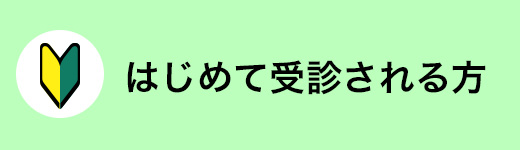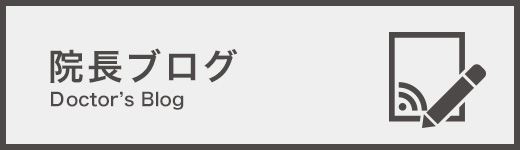不安症と摂食障害
摂食障害における併存精神疾患の中で不安症は最も多いと言われています。
不安とは、未知の危険に対する怯えの反応のことで、何か悪いことが起こるのではないかと身構えている状態です。身体的には交感神経が優位になるため心拍数が速くなったり、呼吸が浅く速くなったりします。
不安自体は生存に必要な反応ですが、それが生活の支障になるほどに強くなっている状態を不安症といい、社交不安症、広場恐怖症、全般性恐怖症などがあります。
摂食障害は、「体重が増えたらどうしよう」と思ったり、「自分は太っているからほかの人からの視線が恐い」などの症状から、不安症との結びつきが強いことは想像しやすいと思います。
併存する疾患同士。どちらがメインと考えるかについては、明確な基準はありませんが、時間的にどちらが先に発症したかが目安になります。もともと不安症をもつ方が体重増加を気にして摂食障害も発症してしまったのか。摂食障害のために不安が高まりいろいろなことに不安になってしまったのかの区別をしていくということです。
不安症状が強い場合には、薬物療法(SSRIなど)を使うことで、どちらの症状も改善することがあります。
逆に、摂食障害から先に発症し、体重・体型に関する不安のみであれば、摂食障害の治療だけで不安症も改善することが期待できます(この場合、厳密には不安症の合併とは診断されないのですが、治療当初は区別がつきにくいです)。
摂食障害の不安に対しては、当院では認知行動療法的な立場にたっていますので、基本的には不安への曝露(=不安にさらされること)と、不安による回避行動(摂食障害においては食べないこと・やせること)をできるだけしないで不安に対処することが治療になります。
不安に対して過食や嘔吐が一時的なリラックス効果(副交感神経の活動)をもっていることから、そのような場合にはいきなり過食嘔吐をやめようとすると逆に精神的な症状が悪化します。
そのような場合には、過食嘔吐の背景にある不安について話し合うことが治療のアプローチとなります。