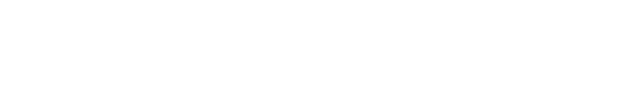摂食障害の病理〜自分隠しと対人過敏
これまで、『聴心記』でも『如実知自心』でもあまり触れていませんが、摂食障害は時代や社会背景の影響を受ける文化結合症候群の側面があることが知られています。
このところトラウマ関連や摂食障害の記事ばかり書いていて、当然、それに関する本を読み漁っているのですが、久々にインスパイアーされた本に、野間俊一先生の『解離する生命』があります。
「自己」と「生命性」を主軸に「ハイマート(Heimat)」という「自らの起源や、最も安心できる場所や、自然な他者との情緒的交流」を巡る解離性障害や摂食障害についての精神病理的論考です。
「ハイマート」はエリクソンのいうような基本的信頼感を保証してくれるHomeと同源の言葉なのですが、一方ではフロイトが指摘したように「底知れぬ不気味さ」を感じさせる強力な力でもあるのです。
さて、その『解離する生命』に導かれながら、すこし、摂食障害関連の部分を読んでいきましょう。
疾患について一般に広く認知され、早期に診断されるようになり、治療法がとりあえず確立された現在も、その数が減少することなく依然として医療者を悩ませ続けている疾患に、拒食症、過食症などを含む摂食障害がある。
我が国では1970年代以降、禁欲と自己管理に基づく結果主義的風潮に煽られたかのように拒食症が増加し、1980年代以降には、結果主義の破綻や欲動の解放とあいまって、その憤懣の表出としての過食症が登場したことにも示されているように、社会のありようが病態に直接反映され、そのことが生物学的過程まで変容させる特異な疾患である。
確かに20世紀末の摂食障害は、究極的な禁欲の姿にも挫折の苦渋に満ちた欲動の解放の姿にも、「自分探し」特有のナルシスが見え隠れする。
『解離する生命』「流れない時間、触れえない自分」
実際、摂食障害の臨床では、古典的な拒食症や過食症は減少し、特定不能の摂食障害、それも「やせ願望・肥満恐怖・ボディーイメージの障害」という摂食障害の中心病理を欠いた「行動異常」や「精神症状」を主徴とする病態が増えています。
「激やせ」という表現によって摂食障害が市民権を得た背景として、現在高校では1学年に数人、大学では女子学生の1割以上の人たちが、なんらかの摂食障害に苦しんでいるといわれる事実が挙げられる。
『解離する生命』「交感する身体」
野間先生は、そのような摂食障害の中で、過食症バリアントとして「むちゃ食い障害」を挙げられています。
しかし、欧米では前世紀の末から摂食障害全体のなかで第一の座を占め、今世紀になって日本でも増えつつある病態が「むちゃ食い障害」である。
明確なやせ願望はなく、自己破壊的な誘発嘔吐も下剤乱用も運動過多もなく、どちらかというと、”一気食い”ではなく”だらだら食い”によって空白の時間を埋め、その結果肥満傾向を示し、通常の神経症的疾患なら期待されるような心理社会的誘因を本人の主観性格には見いだすことが困難なこの病態において、苦悩する者の「自分」はすでに探すべき対象の座を降りて霧散し、しかもそのこと事態が一つの救いとなっている。
ここにあるのは「自分探し」ならぬ「自分隠し」である。
『解離する生命』「流れない時間、触れえない自分」
過食症の病理の中心は、対人関係療法では、「対人関係上の役割をめぐる不和」と「対人関係の欠如(対人過敏)」の2つを維持因子(習慣に「はまりこむ」要因)として重視しますよね。
「対人関係上の役割をめぐる不和」では、重要な他者との役割期待のずれが慢性化し、蓄積された無力感や絶望感、そこから生み出される負の感情から逃れるために自分を麻痺させる手段として過食は用いられますし、「対人関係の欠如(対人過敏)」では、一見対人関係は問題ないが表面的であり、慢性的な自己評価の低さを抱えており、安定した対人関係を維持することが困難で、自己主張ができないため、常に自分が我慢を抱え込み、過食で自分の苦しさを麻痺させている、というように文脈を読み解いていきます。
この2つに共通する「自分を麻痺させる手段」を、野間先生は「自分隠し」とおっしゃっていますよね。
本来、自己というものは一つのはずである。しかし食を病む者にとっては、自己はつねに二重化する。
つまり、人から見られることを意識しすぎるあまり、「見られる自己」と見られていることを意識する「本当の自己」が、乖離してしまっているのである。
彼らは、弱々しく情けない「本当の自己」を隠すために、「見られる自己」を綿密に作り上げようと日々の悲痛な努力を続けている。その努力により、自己はますます引き裂かれ、悲鳴をあげる。「本当の自己」を隠すための「見られる自己」の突出という事態に潜在するのは、一見本当の自己を否定しているかに見えて、じつは脆弱だが愛おしい自己というものへの過剰な意識である。
『解離する生命』「愛のキアスム」
対人関係療法でいう「対人関係の欠如」をスコット・スチュアートは「対人過敏」と呼んでいますが、自己評価の低さを抱えた「本当の自己」を「見られる自己」を意識することで隠そうとする行動が水島先生がおっしゃる「見た目が気になる症候群」ということですね。
野間先生は過食症の根底には過敏な自己愛が潜んでいるとおっしゃいます。
過食症者がひたすら食べ続けるのも、自傷症者が繰り返し自らを傷つけるのも、「自分探し」ではなく「自分隠し」のためだとすれば、彼らにとっての”自分”が主体の相対化という時代の要請に応じて拡散していると見るよりも、なんとか拡散させて隠し通さねばならないほど”自分”が独特の迫力でもって圧倒してきていると考える方が自然である。
自分の経験を、まさにほかならぬ自分の者だと”自己化personification”(ヴァンデアハート)し、過去でも未来でもない今の経験だと”現在化presentification”できるのは、自分以外の他者から——対峙する個別的他者ではなく連帯する無名の他者から——それを全面的に了解されているという安堵に裏打ちされる必要がある。
自らの経験について安堵を与える無名の他者とは、具体的な場所や集団や思想を越えた、あらゆるナショナリズムやポリティックスとは無縁の、きわめて私的かつ普遍的な「ハイマート」の経験である。”自己化”や”現在化”の崩れは慢性的な心的外傷体験に伴った解離症状の主要な特徴だが、それは、予告も必然性もなく不意打ち的に到来した飛散が、歴史の無力を痛感させ他者への信頼を剥奪する。
そして、”自分”という概念とそれを保障する”ハイマート”の経験自体が、時間や他者への絶望を想起させ外傷を再演するリマインダーとなるのである。
『解離する生命』「流れない時間、触れえない自分」
ちょっと難しいですが、低い自尊心を抱えた「本当の自己」に対して、「見られる自己」という「ハイマート:安全基地」を作り上げ、安心得ようとする行為そのものが逆にリマインダーの経験となる、つまり過食症に関しては維持因子となる、ということをおっしゃっていますね。
次回は、摂食障害と関連する「自己愛」の病理について見ていきます。
院長