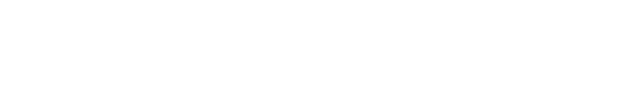摂食障害が治るということ
摂食障害の対人関係療法による治療も折り返し地点をすぎ終結期が見えてくるようになると、患者さんは、症状に一喜一憂されるようになることが多いのです。
たまたまひどい過食が起きるような出来事があると、「まだ治ってない」と焦りと不安でいっぱいになってしまいますよね。
無理もないことなのですが、そういうときこそ「ストレス解消としての過食」の対人関係療法での治療の原点を振り返る必要がありますよね。
それは
この病気の治療の大原則は、あくまでも、症状にとらわれないということであり、同時に、症状から自分のストレスに気づくことなのです。
ということですし、
病気のレッテルを貼って「過食はがまんしなくてよい」「しばらくは食べ物を吐くのも仕方がない」というふうに認めることと、「病気を言い訳にしないできちんと変化を起こす」
という「病者の役割」としての治療の取り組みに戻るということですよね。
しかし、一方で
しかし、本章で見てきたような〈回復〉のあり方(註:食事へのアプローチ(『過食症の食生活の改善』参照))を強調することは、摂食障害に苦しむ人々に自力での回復を迫ることにつながってしまう可能性がある。
ここには、苦しむ人々が、回復できるのに回復しようとしない人というレッテルを貼られ、抑圧されていく余地が残る。
現代では、「主体性」の安易な称賛は、容易に「自己責任論」に絡め取られてしまうのだ。
『摂食障害の語り〈回復〉の臨床社会学』中村英代・著 新曜社
という「自己責任論」にみられるように、症状をコントロールすることを手放し、「早く健康な状態になるため治療に協力すること」という「病気の人ならではの義務(病者の役割)」が、責任論と混同されてしまう危険があるのです。
その根底には「医学モデル」が明確でないという問題がありそうです。
その視点で『摂食障害の語り〈回復〉の臨床社会学』で触れられている「〈回復〉のあり方」をみてみると
過食や嘔吐がなくなった時点が摂食障害からの〈回復〉と見なされることが最も多かったが、人によっては、さまざまなこだわりがとれた段階を〈回復〉と見なしていたり、逆に、過食をする自分自身を受け入れた段階を〈過食〉と見なしていたりと、幅があった。
『摂食障害の語り〈回復〉の臨床社会学』中村英代・著 新曜社
というふうに、どうしても症状が指標にされてしまいます。
つまり対人関係療法で行っているように「病者の役割」や症状と人格を区別する「医学モデル」を明確にしないと「自己責任論」に陥ってしまい、患者さんの罪悪感を刺激し病気に閉じ込めてしまうという悪循環が起きやすいですよね。(周囲の人もそうなりがちです)
さて、「摂食障害が治る」ということは「過食や嘔吐がなくなった時点」ではなく、また、「こだわりがとれた段階」でもなく「過食をする自分自身を受け入れた段階」でもなければ、いったいどういう状態なのでしょうか。
水島先生は
「病気が治る」というのは、「体型が気にならなくなる」ということではなくて、「体型へのこだわりが生活を乱さなくなる」ということだと考えて下さい。
(中略)
拒食や過食嘔吐などの症状が再発したときには、自分が抱えているストレスとしっかりと考え、正しいコミュニケーションによってその問題を解決していく、という方法が常にとれるようになれば、「摂食障害が治った」と言えるのです。なぜなら、どんどん病気が重くなって生活を乱すことにはならないからです。
『拒食症・過食症を対人関係療法で治す』水島広子・著 紀伊國屋書店
というように、
○「医学モデル」に基づく「障害がなくなった状態」
○対人関係療法によって、新たなスキルが身について「障害を起こさなくなった状態」
の2つを「摂食障害が治った」状態と定義されています。
つまり「過去の辛い体験や現在の病気が、今後の人生を損なわなくなる」という治療の目標そのものが、とりもなおさず「摂食障害が治った状態」であり、対人関係療法による治療が終わった後に取り組んでいくことは、「再発のリスクを抱えた健康な人」という役割であり、
この病気(摂食障害)の治療の大原則は、あくまでも、症状にとらわれないということであり、同時に、症状から自分のストレスに気づくことなのです。
という、今後も引き続き取り組んでいく姿勢であり
症状がひどくなったときに「もう絶対に治らない」とその波にのまれるのではなく、症状がひどくなったときこそ「自分のストレスを見極めてやろう」と積極的に取り組んでいく姿勢が必要です。
この姿勢は病気が治ってからもずっと必要になるものです。
という、自己責任論に絡め取られない「主体性」のあり方ですよね。
つまり、摂食障害の治療においては、「治し方(方法)を知っている」だけではなく、その人に合った「治り方(ゴール)も知っている」治療者を選ぶことが非常に大切だということですね。
院長