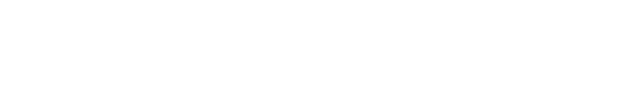適応障害の診断と治療の実際
『適応障害は流行しているんですか?』で、症状の重症度、気質や性格要因、ストレス因の状況と強度あるいは持続性などを詳細に検討し、その人にあった治療のすすめ方を考えていく必要があることを説明しました。
本来の「適応障害」は、地位の変化、死別、身体疾患罹患などの比較的日常的な出来事に対する順応期に、抑うつ・不安症状、あるいは、行為面の障害などが生じることによって規定されます。
たとえば、昇進や部署異動などの変化に伴って、反応性に抑うつ状態や不安症状、あるいは遅刻や無断欠勤など行為面の障害が認められる場合に、「適応障害」と診断されます。
つまり、「変化」というストレス因に対する順応期に生じる反応が、日常生活に影響をあたえるようになった状態を適応障害と診断するのです。
「適応障害」の診断基準では、ストレス因に対して通常予測される程度をはるかに超えた苦痛、あるいは社会機能の著しい低下を伴う障害のいずれか1つを満たすことが要件となっていました。
比較的日常的な出来事に対するストレス反応を過剰に医療の対象としないように、この2つを必須条件にする案もあったそうです。
「適応障害」の診断が正しければ、誘因となったストレス因が解消されてから6ヵ月以上、あるいはストレスが持続していても新しい適応水準に達したときには症状が消失するとされています。
つまり、「適応障害」は反応性の状態であり、業務軽減などの対応で順応するまで待てばいいわけで、多くは治療不要なのです。
本症(註:「適応障害」)は、ストレス因によって症状が出現するが、どの診断基準も満たさないようなケースに該当するもので、ある意味、「ごみ箱診断」的な要素が強い概念であった。
しかしながら実際には(これは多分に想像であるが)、臨床的には安易に用いられ、心因性・反応性の軽いうつ状態や不安状態(本来は、適応障害ではない!)に対して過剰にあてはめられていたようであり、7年後のDSM-III-Rの改訂では、上記の基準Dが「不適応反応は、6ヶ月以上持続しない」と期間を限定するに至った。
診断上の問題点は、ストレスがなくなって半年経っても症状が改善しない状態に対して、本症の過剰診断・誤診断がなされやすいことである。
『ICD-10精神科診断ガイドブック』中山書店
上記に加えて、「ICD-10が6ヶ月以内に新たな適応水準に到達できない患者も含めていることであり、言い換えれば、ストレス因子に対する心理的反応であっても人格特性等の患者側の要因によっては経過が長期化してしまう」ことが、「適応障害」の過剰診断・誤診断がなされやすい要因として指摘されています(『ICD-10精神科診断ガイドブック』中山書店)
つまり、『はじめての精神科』で「パーソナリティの偏りに由来する抑うつ状態(治療というよりは自分の心とのつきあい方を学ぶべき)」とされている状態も「適応障害」に含まれてしまっていまです。
現在、「パーソナリティの偏りに由来する」適応の障害(不適応状態)は、臨床で頻繁に遭遇します。
クロニンジャーの気質性格理論では、生まれつきの「気質」と、後天的に学習習得されたスキルなどの「性格」によって「パーソナリティ(人格)」が形成されると考えられています。
気質は出来事の体験の仕方を規定し、性格は出来事の意味づけを行うことで、気質をコントロールします。つまり、気質と性格があいまったパーソナリティとは、状況に対する対処の仕方です。
それまでに身につけた対処法(学習習得した性格)で状況に対処できなかったとき、つまり順応反応・適応反応が起きている間は、生まれつきの気質特性で対処しようとします。
ところが、生まれつきの気質に「自閉症スペクトラム(ASD)」特性があると、認識・感情調節・対人関係の問題が引き起こされやすく、不適応状態は遷延してしまうのです。
このような状態は、静かな忍耐、あきらめ、焦りと反抗、不機嫌、無気力、虚栄的、郷愁、悔恨、おそれなど、さまざまで、場合によっては行為面での障害も生じる「抑うつ反応」や、抑うつ気分自体が外部の状況やストレスによって変動しやすく、不安がうつ病像の中心となる「不安うつ病・抑うつ神経症(神経症性抑うつ)[現在は気分変調症]」など呼ばれます。
上記とは別に、過重労働や長時間労働など、あるいは上司や部下さらには同僚との人間関係を引き金に、さまざまな精神症状を呈した場合も「適応障害」と診断されてしまう傾向があるのです。
過重労働や長時間労働が誘因であれば、本来なら「神経衰弱」と診断されます。
「神経衰弱」は、精神的な労働の後に顕著な精神的易疲労性が現れるもので、職業や日常生活上の活動能力の低下に結びつきますから、容易に適応障害と診断されてしまいます。
「神経衰弱」の症状も、余計な考えに妨害されることによる注意力散漫や集中力低下、思考あるいは能率低下、アンヘドニア、知覚過敏、記憶力減退などであり、「適応障害」の抑うつ反応あるいは反応性不安と誤診されやすいのです。
「神経衰弱」の治療は短期間の休養と労働環境調節であり、抗うつ薬や抗不安薬が投与されることによって、適応障害と同じように病態は遷延しやすくなります。
職場の対人関係の問題は、本来なら「心因反応」あるいは「重度ストレス反応(重度ストレスへの反応)」と診断すべきです。
一般に、「心因反応」とは、別名「体験反応」とも呼ばれ、広義には心理的原因によって反応性に生じた一過性の精神状態全般を指す広範囲の概念であり、呈する症状としては、不安、抑うつから幻覚、妄想までさまざまである。一方、狭義には、心因性精神病のみを指す。
ちなみにJaspersは、体験反応に関する以下の3つの指標をあげている。
- 原因となる体験がなければ反応的状態は生じない。
- この状態とその原因のあいだに理解可能な関連性がある。
- この状態の時間的経過はその原因に属しており、原因が除去されれば状態も消失する。
したがって、不安や抑うつ、あるいは行為の障害等を呈する「心因反応」は、F43(註:重度ストレス反応および適応障害)と診断されることが多い。
『ICD-10精神科診断ガイドブック』中山書店
人間関係がきっかけとなった「心因反応」や「重度ストレス反応(重度ストレスへの反応)」に対しては、脆弱性とレジリエンス、そして、「相手の言動に自分はどう対応したのか、その反応に相手はどのように反応したのか」など、対人相互作用性と対人相互反応性の「関係性」を診ていくことで、人間関係への対処が可能になるのです。
このように、一見「適応障害」と安易に診断されてしまうような病態でも、詳細に診ていくと背景にある状態と対処法の違いが見えてきます。
こころの健康クリニック芝大門で行っている、このような詳細な診断にもとづいて対処の仕方を考えていくことが、働く人たちに不利益をもたらさない精神科臨床のすすめ方なのです。
院長