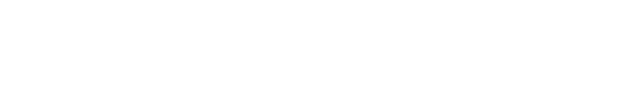摂食障害の対人関係療法による治療の特徴
2011年に双極II型障害、PTSD、神経性過食症と診断し、神経性過食症を主なターゲットに対人関係療法を行った患者さんがいらっしゃいます。
この患者さんは、うつ状態・拒食症の診断で治療を受けられていたのですが、対人関係療法を希望し三田こころの健康クリニックに転院してこられたのでした。
対人関係療法による治療では神経性過食症に焦点を当てつつ、同時にPTSDと双極II型障害に対する心理教育を行い、20回の治療が終了しました。その後、1ヵ月ごとにフォローしていましたが、治療開始から1年後の2012年には過食・嘔吐もフラッシュバックも気分の波も消失し、現在まで再発もなく、近況報告のため定期的に受診してくださっています。
先日、1年半ぶりに受診された患者さんとが、静かな時間が流れる面接の中で、こんなことを話されました。
「8年前に先生が治療の中でおっしゃってくださったこと、まだ覚えています」と。
患者さんのこの言葉にインスパイアーされ、私がどんなことを考えながら神経性過食症や過食性障害の対人関係療法による治療を行ってきたのか、この13年間の軌跡をふり返ってみました。
2008年から対人関係療法の勉強会に出るようになり、摂食障害に対する対人関係療法による治療を始めました。
対人関係療法による治療を始めた当初は、それまで勉強していた他の心理療法の技法は一切封印して、対人関係療法の枠組みだけで治療しようとしていたのです。
神経性過食症や過食性障害、気分変調症だけでなく、解離性健忘を伴う解離性障害、不潔恐怖と確認を伴う強迫性障害、全般性不安障害とパニック障害の合併例、奥さんと娘さんを亡くし天涯孤独になった遷延性悲嘆に伴う身体症状、双極II型障害に合併した過食嘔吐、頻回の自傷と自殺企図を繰り返すアタッチメントの問題を抱えた患者さん、アスペルガー症候群の患者さんなどなど、さまざまなケースに対して対人関係療法を使ってみました。
もちろん、うまく行くこともあれば、治療に難渋することも数多くありました。
その中で、過食嘔吐を伴う摂食障害(神経性過食症)や過食性障害(むちゃ食い症)と診断されていた人の中に、過食の定義を満たさないダラダラ食い(大食あるいはエモーショナル・イーティング)の人や、1日3食の食事摂取ができてない飢餓大食の方が多くいらっしゃることが見えてきたのです。
さらに、摂食障害とともに対人関係療法の適応にならないといわれる強迫性障害を併存している人が6割近くいらっしゃることを論文で読み、実際、治療に難渋したケースを見返してみると、ほとんどが強迫性障害や、非障害性あるいは障害性の自閉症スペクトラムを合併したケースであり、神経性過食症や過食性障害の6割の人は対人関係療法にならないのか!と愕然としたこともあります。
ちなみに、対人関係療法のマニュアルには、対人関係療法の適応にならない以下の除外基準が設けられています。
除外基準(水島2009を一部改変)
○ 躁状態や精神病状態の既往
○ 物質関連障害および嗜癖性障害群
○ 器質性脳障害
○ 重篤な身体疾患や低体重(BMI<16;*日本人標準BMIを20とした場合(切池, 2012))
○ 対人関係療法による治療が困難と判断した場合
強迫性障害および関連障害群(チューイングを含む)
神経発達障害群(自閉症スペクトラム障害、知的能力障害、コミュニケーション障害)
希死念慮、自傷行為の頻発
回避性パーソナリティ、あるいはスキゾイドパーソナリティ
これらの疾患は、自分自身との心との親和性が低く、定型的な対人関係療法のやり方ではうまく進められなかったのです。
『メンタライジング・アプローチ入門——愛着理論を生かす心理療法』の著者である上地先生がFacebookにこのようなことを書かれていました。
自分の臨床の場では、とても本格的な精神分析的心理療法に適したクライエントは来ない。このケースはと期待すると、あまりにメンタライジング能力が低すぎて、メンタライジング能力の極めて基盤的な所を育てる面接になる。
そのような状況で、「~先生はまともな精神分析的心理療法をやっていない」とか「~先生はきちんとした精神分析の訓練を受けていない」といった評価が周囲で語られるのを聞くうちに、こんなふうに言われず、自分に矜持を持つためには、この枠から脱け出すのがよいと思ったわけです。
私の場合も上地先生と似たような紆余曲折とも言える臨床の航跡をたどってきたのですが、中でも素直でコミュニケーション能力が高く、自分の心の動きや対人関係で向き合う重要な他者の心理状態に好奇心を持つことのできる摂食障害の患者さんは治りやすいなぁ、と漠然と感じていました。
なんとか対人関係療法による治療効果を上げようと、治療導入前に治療の土台作りとして自己内対話の仕方を教える心理教育を始めました。しかし、定型的な対人関係療法ではこのような心理教育は行いません。勉強会で「対人関係療法では、そういうことは行わない」と指摘されたこともありました。
と同時に、対人関係療法の適応にならないとされているケースを数多く経験する中で、対人関係療法の弱点も見えてきたのでした。
たとえば対人関係療法で治療者は、「特定の方向に患者を導かない」「認知に焦点を当てない」とされています。認知の仕方が誤っていたとしても、それは症状と位置づけ、症状は本人のコントロール下にないとスルーします。
また、対人関係療法の治療者は、患者の代弁者としての温かい立場を取ることがモットーですから、他責的な患者であっても患者の認識を尊重することが強調されます。
これによって安心・慰めを求め、苦痛を伴う内省を回避する「愛着のパラドックス」が起きやすく、また、患者(+治療者の連合)がサポーターである重要な他者である家族に無理な協力と負担を強いることで、当然のことながら不和が長引いてしまう、という致命的な結果を引き起こすことも経験しました。
2015年に『私はこうして摂食障害(拒食・過食)から回復した』『摂食障害から回復するための8つの秘訣』が出版されました。
「摂食障害の部分(エド)」と「健康な部分」との葛藤と和解がテーマのこの2冊は、それまでフワフワしていたパズルのピースがピタリとはまったような、私の対人関係療法臨床に大きな衝撃をもたらしました。
従来の摂食障害治療の対人関係療法では、重要な他者との関係のうち病気の維持に関わっている因子である「欠如(親密さの回避と対人関係の不足)」あるいは「不和(対人関係上の役割をめぐる不一致)」に焦点を当てることが多いのです。
欠如は不和の行き詰まり(交渉を諦めて心の中に閉じこもっている状態)と考えられていて、再交渉に持っていくことが治療になると考えられていました。
ところが、自分の心の中で起きている摂食障害(エド)と自分自身(健康な部分)の不和(葛藤)があるために、エドが自分に下しているのと同じような批判を他者からも受けるかもしれないと、対人関係から遠ざかる欠如が起きていたのです。この視点は、のちに『メンタライゼーションでガイドする外傷的育ちの克服』で明確になりました。
つまり、対人関係要因で「対人コミュニケーションの希薄さ」により「満たされなさを感じていたり、維持が難しかったり」して「慢性的な自尊心の低さを抱えている」ことの背景に、「内受容感覚への気づき困難と気分不耐による気分解消行動」、つまり「ネガティブな情動や思考への接触回避方略」などの個人的要因があるということがわかってきました。
また、他者との再交渉ができたとしても、自分の中にあるエドは辛辣な批判を続けますから、ふたたび同じように対人関係を避けて遠ざかるか、あるいは逆に、他者に依存的になってしまいます。
ということは、他者との再交渉を進める前に、自分の中で起きているエドと健康な部分との和解を進める(自分との関係を改善する)必要があるのではないか?と考え続けていました。
この考え方は『グループ対人関係療法』で、①自分との関係を改善する、②行動の仕方を変えていく、③他者との関係を改善する、とすでに解説されていたのです!
最近出版された『鬱は伝染る。』にも、自分との関係の改善(認知パターンの変容)、行動の仕方を変えていく(行動パターンの変容)、他者と関係の改善(関係性の質の変容)について、こう書いてあります。
しかしながら、時が経つにつれて、生物学的アプローチだけでは限界があることが明らかになってきた一方で、薬物を使わずに提供できるある種の心理療法(いわゆる「会話セラピー」)がうつ病の治療に効果的であることが明らかになってきました。
よく研究された多くのセラピーが、効果的な治療の鍵となる以下の3つの洞察を明らかにしてきました。
「考え方の質」と、「関係性の質」と、「効果的な行動を積極的に学ぼうとする気持ち」は、いずれも抑うつからの回復にとってきわめて重要です。ヤプコ『鬱は伝染る。』北大路書房
また,英語の本ですが『The Treatment of Eating Disorders』に、『グループ対人関係療法』の著者の1人であるウィルフリイが、「対人関係療法では、治療外での対人関係を修正するのを援助するために、いかなる技法も禁止されていない」「対人関係療法はすでに他の治療様式の側面をシームレスに取り入れている」と書いていました。
このことに勇気づけられ、こころの健康クリニックで行っている対人関係療法による治療では古典的な対人関係療法が準拠する急性期疾患に適応される医学モデルではなく、慢性疾患にも適応可能な生物-心理-社会モデルに基づき、さまざまな心理学的な技法を用いて、①自分自身との対人関係の改善(認知—行動パターンの変容)、②二者関係の改善(コミュニケーションの改善と対人関係の質の変容)、③集団との関係の改善(問題解決スキルと遂行スキルによる現実対応)の3つの次元の対人関係を治療の焦点とするようになったのです。
この3つの次元の対人関係は『複雑性トラウマ・愛着・解離がわかる本』でも言及されていますので、対人関係療法の土台として、必要不可欠な視点だといえると思います。
院長